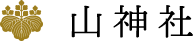
| 崇徳天皇の永治元年(1141) | 摂津国の住人、現宮司家の祖、小山田清寧(きよやす)が勧請 |
|---|---|
| 元亀二年(1571) | 小山田清寧の子孫である浄円(当山派別当)が御神体を平泉に奉遷途中、 色々な経緯があり小牛田に鎮め祀りました。 |
| 天正三年(1575) | 祠を建て御神体を鎮め奉る |
| 寛文二年(1662) | 自円の孫、宥鏡の時、仙台藩において新たに小牛田駅を開設するに際して、南小牛田村町屋敷の地に社殿(間口9間・奥行4間)を造営・遷座 |
| 元文元年(1736) | 宥鏡6世の孫、尊順の時、村内で大火があり、類焼 |
| 元文五年(1740) | 社殿 再建 |
| 寛政四年(1792) | 尊順の孫、憲牛の時、社殿の改築を起工 同年、山神永代献膳碑建立 |
| 文化六年(1809) | 社殿造営完成(間口9間・奥行4間) |
安土桃山時代、御神体を鎮め奉ると御祭神の御神徳を求め、多くの人が訪れ、信仰が広がり、御鎮座より100年も経過しない内に、寛文2年(1662)、現在の社殿より二回りも大きい(間口9間・奥行4間)の社殿が造営されました。 1700年代には男性を中心にした【山神代参講】、婦人を中心とした【山神代参婦人講】が結成されました。 明治になり、小牛田町の総氏神として、ありがたくも国(太政官布告)より指定を受けました。同時期、下小牛田鎮座の無各社日枝神社、西原鎮座の八幡神社、町屋敷鎮座の郷社日枝神社、山崎鎮座の神明社を合わせお祀りし、山神社は郷社に昇格致しました。 |
|
| 明治四十一年八月 | 町内の大火事の際全焼 社掌・憲一郎、仮宮に御神体遷座 |
| 大正六年 | 火災後、社司・昇が境内地として現在地を取得 本殿・幣殿を造営、拝殿・社務所を仮設し大正6年12月26日遷座祭を斎行 |
| 同年十二月二十六日 | 遷座祭が斎行される 鎮守の森育成の為、松の木100本を植樹する |
| 昭和四年~九年 | 拝殿・参集殿を新築(昭和4年に拝殿、昭和9年に参集殿新築) 合わせて神域整備も行われる |
| 昭和五十四年 | 造営より半世紀の歳月を経た事で雨漏りが発生 社殿屋根銅板葺替工事を行う |
| 平成四年 | 平成御大典記念として、手水舎、透塀を造営 |
| 平成十一年 | 今上陛下御即位十年記念として社務所の造営事業を行う |
| 平成十五年 | 御即位十五周年記念として大鳥居建立 |
| 平成二十三年三月十一日 | 東日本大震災 震度7の大地震で大鳥居が損壊 |
| 平成二十四年十月十二日 | 大鳥居震災後再建 |
| 平成二十九年 | 遷座百年記念大祭 記念事業の概要 神前燈籠二十基参道に設置・殿内調度品新調・奉名碑設置 |
【御神体についての口伝】 |
|
「山神講」とは山の神様(木花之佐久夜毘売命)の御加護を願う信仰者の集まりです。“祈願成就の際には神恩感謝の御礼参り”をいたします。
「山神講」には山中安全を願う山林業・鉱山・温泉業など男性を主とした「山神代参講」と木花之佐久夜毘売命の御事蹟の安産・子授け・子育てを願う「山神代参婦人講」の二種類があります。
「代参講」とは講員の代表者が小牛田の山神社へ参拝いたします。祈祷を受け、御札・撤下(御供物・御神酒)を授与します。
講員は宿(当番の家)・集会所に集まり、「掛け軸」・依代(観音像・赤子を抱いた御姿)に代表者が授与してきた御札・撤下・お供え物をして、山の神様を遥拝(遠くから拝む)する敬神の念の篤い信仰者の集まりです。
「山神講」は神事を通して直会の時、お下がりを頂きながら、衣・食・住の知恵を学び、伝統文化の継承の場であり、そして、楽しいコミュニケーションの場でもあります。
小牛田の山の神様の掛軸
 江戸時代~明治時代 |
 大正時代~昭和時代 |
 昭和時代 |
小牛田の山神様の掛軸は御祭神の御神徳や御姿を記した(書いたり、刷ったり)もの。
宿(当番の家)・集会所の床の間に掛けて、山の神様を遥拝する(遠くから拝む)もの
【時代と共に信仰形態の変遷で危惧されること!祈念すること!】
山の神講の減少は敬神の念の希薄な人々に精神文化(まつり・人生儀礼)の伝承が困難になることが危惧されます。併せて、良き伝統文化・美風の伝承も困難になると思います。
現代は科学・経済の発展、核家族化が進み、良き伝統文化が伝え難くなっています。
このような時代だからこそ、山神代参婦人講中が減少している中、多くの講中が残り、山の神様の御縁日には皆が集まり山の神様の御加護を願い、神事を通して日本の良き伝統文化・美風を継承する山神代参婦人講を次の時代へ守り伝えたい。
御詠歌とは、和歌や短歌に節をつけたもので、山神社では数々の御詠歌が残されています。

先に述べたように1700年代には男性を主とした【山神代参講】と婦人を中心とした【山神代参婦人講】が結成されておりました。大正・昭和の代までは山神講1千組、山神代参婦人講5千組余りの崇敬者が小牛田の地まで代参をし、講員は掛け軸を通して山の神様を遥拝。何年かに一度講員全員が揃って小牛田山神社へ参拝した記念に石碑を建立しました。又、石碑を通して遥拝(遠くから拝む)する信仰形態を継承してまいりました。
山の神信仰は、仙台藩の時代より篤い信仰があり東北一円、北海道まで広範囲に広まったことが各地に残る石碑が物語っています。
宮城県遠田郡美里町彫堂に残る石碑




岩手県西磐井郡平泉町長島石合【山神宮】



蔵王の連峰の麓の人々は蔵王権現の御加護はもちろんの事、集落ごとに八百万の神々、そして、江戸時代から小牛田の山の神様も信仰している敬神の念篤い軌跡を残しています。
蔵王刈田峰神社の境内には江戸時代の古い台座に乗った「赤子を抱いた立像」「木花之佐久夜毘売命」をイメージにした立像が彫られた二基の石碑があります。
向かって左側の「赤子抱いた像」石碑は年代不明です。
ところが、「赤子を抱いた像」の年代不明が多い中、蒲生藩主和田氏が伏見稲荷信仰と小牛田の山の神様を合わせて信仰した軌跡が蒲生地区に今も大切に残っています。
それによると、「赤子を抱いた像」の石碑は安永5年(1777)前後のものと推測されます。
向かって右側の石碑は「安産守」
「聖観世音」「十二」、台座には「世話人」「十名位の名前」が刻まれています。
この確認から、安産を願い、山の神様の御縁日十二に世話人はじめ、名前が刻まれた人たちが小牛田の山神社に参拝し、その記念に石碑を建立したことがうかがえます。
この集落には1770年代頃から「山神代参婦人講」があった事を物語っています。
この二つの石碑から、江戸時代の信仰は神仏習合、本地垂迹説の思想の影響を受けて、コノハナノサクヤヒメノミコトの御神体に観音菩薩像を石に彫り、信仰した時代背景がみえます。
蒲生地区の人々は未曾有の3・11の震災で甚大な被害を受けましたが鎮守様(氏神)の再建に努められ、境内整備をして先人たちの祈りの心を継承しています。 先祖代々の信仰の石碑の数々をがれきの山から大切に取り出し、建立されています。
その中に安産の神「山神」の石碑が今の時代も地域の人達に見守られ新しく再建した社殿前に立ち続けております。
そして、令和となったこの時代に講が解散しても尚、安産・子授け祈願に小牛田の山神社へ参拝に訪れる人々が絶えません。
宮城県仙台市宮城野区蒲生高砂神社内【山神】


宮城県仙台市宮城野区南蒲生神明社【山の神】


3.11の震災の時に地域の石屋さんの所で、たった1個だけ残った御影石。「前の石碑」は井内石で出来ており、新しい石碑より「もう一回り大きい石碑」です。

震災後、総代の遠藤喜一さんが御影石の石碑奉納 平成23年3月11日
遠藤さんは地域に貢献している婦人達が昔から小牛田の山の神様を信仰しており、「山神」の石碑が震災で流され、無念の思いでいることを知り、又遠藤さん宅でも3人のお孫さんに恵まれ、御加護賜り感謝の念で石碑を奉納されたそうです。
宮城県仙台市宮城野区大和神社(和田大明神)【山神】



「山神」「小牛田」「文政3年」
「赤子を抱っこした像」「安永5年」
「山神」※写真左
自然石
高さ120cm前後
下巾50~60cm前後
上巾50cm前後
「赤子を抱っこした像」※写真右
高さ50~60cm前後
巾35cm前後
厚み10cm前後
1661年、蒲生領主和田織部房長は家臣30人を連れて多賀城紅葉山の館へ移住した際に氏神として伏見稲荷大社の神様を分霊し、勧請しました。
和田氏が大和(奈良)出身ということから「大和神社」と称しました。
その後、「赤子を抱っこした像」が彫られた石碑を安永5年(1776)に建立、「山神」「小牛田」「文政3年」が彫られた石碑も建立し安産の神「小牛田の山の神様」として篤い信仰をしてきたことが伺えます。
和田氏は明治政府の政策により新田地域を去る際に鎮守の神として地元の人々に寄進され、今日に至ります。
高度成長期、昭和30年代の末期から40年代にかけて都市計画・団地造成で、山を崩し、山が無くなり、地域の景観が一変していきます。 地域の人々は開発の中、先人達が山の恵みに感謝し畏敬の念で建立していた石碑を捨てる事無く、道端や公園の一か所に建立しました。
中山山の神公園 仙台市青葉区中山2丁目102-68【山神】八基の石碑
昭和59年3月31日開園



北山霊園 仙台市青葉区北山2丁目10-1【山神】



神社、寺院の境内にその地域の人々が山神社の祭神・木花之佐久夜毘売の御加護を願い、厚い信仰をしており、参拝記念に建立して、遥拝した信仰の足跡です。
【榴岡天満宮】 仙台市宮城野区榴ヶ岡105-3鎮座
「山神」「小牛田」「嘉永3年」「二日町女講中」10人位の氏名が刻まれた石碑1基



【舞臺八幡神社・蛸薬師如来】 仙台市太白区長町4丁目
「山神」「小牛田」「長町」「文化6年 女講中」「大正8年」




【旅立稲荷神社】 仙台市若林区若林2丁目
「山神」「文政4年」「明治9年」



県内でも登米市中田町は特に信仰の篤い地域です。それは、町内の講の総数149の内79と、実に半数以上が山神講であることからも伺えます(「平成16年 行政区毎の講の調査」による)
その地域の石森字桑代の人々は、山神社に代参、そして、八幡様の境内地の山神の石碑に参拝。その後、桑代集会所に集まり、【掛軸】【赤子を抱いた御姿の依代】【婦人講中の御札】【神恩感謝の御供物】を供え、御加護に感謝、そして各々の祈願成就を願います。
宮城県登米市中田町石森字桑代【山神】




宮城県石巻市大瓜字八津山【お堂の中の祠と御神体】(令和3年撮影)
本木利茂さん(72)の曽祖父勇士さんが建立したお堂の中に「仏像」「お軸」「祠」が祀られていました。
それは神仏習合の時代を物語っています。


宮城県気仙沼市本吉町下川内鎮座
【山神社・寛政12年勧請と伝わる。写真は大正12年建立】



岩手県大船渡市赤崎町字長崎【祠と山神社お札、昭和43年に建立】(令和3年撮影)


岩手県奥州市水沢に鎮座【山神社】

岩手県一関市赤萩字笹谷【祠と奉納されたおまくら(両脇)】



この地域の婦人たちは、昭和60年まで代参していた。その後は個人で参拝するようになった。
岩手県奥州市水沢羽田町外浦鎮座【山の神神社】





北海道士別市東8条北1丁目九十九山【士別山神社】

「士別神社公式ホームページ・境内社・碑」より抜粋
由緒古く明治35年、宮城県小牛田山神社を崇める屯田兵夫人方によりご創祀。
安産の神の御霊徳のほか造材木材関係の人々や登山家の守護神として信仰されています。平成5年北町地区の同様の山神講御神座を合祀。住吉鳥居と玉垣に囲まれ、1月12日士別地区林産協同組合主催で例祭が行われます。